
最近は過去記事振り返ったものばかりですが、これは二年前に、過去記事3つの振り返ってもの。
まあ、どれもそうだよなって感じです。
今回の転載元はこちら

ブログで編集したり、記事を書いたりしているとときどき、過去の記事をサジェストしてくれたりします。
その中で、2つの記事が目に入りました。
1つめはこれ
記録を見ると2014年5月7日に書いたものです。
現場の教員から特総研に移って6年目。教員を離れて気がつくのは、その魅力について書いています。
ここには書いていないですが「子どもと一緒にいること」「給食があること」「体を動かすこと」の3つが教員を離れるとできなくなるなと感じていました。今は2つめの給食はありませんが、学生と一緒にいるといろいろな刺激をもらえるので、とても楽しいですし、大学って結構広いので、体を動かします。(スポーツ科学部なので、それなりに体を動かす機会もありますが専門じゃ無いのでそれほどでは)
さて、上記のエントリーではこんなことを書きました。
逆に考えると現役の先生方は誇りを持って自分の実践を語れるので羨ましいかぎりです。
「現役」って、そういう意味ではすごいことですよね。
いろいろとやりにくいこととか、不合理も感じると思いますが、子どもたちと直接関わることの凄さはとてもステキだと思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私自身は後悔していませんし,いろいろな先生方との交流を通じて子どもたちともふれあえるとは思っています。
ですが,ぜひ先生方には今やっている実践を自信を持って語って下さいね。
本当にそう思います。ダイレクトに変わってくる子どもたちを目の前にできるってステキなことです。障害が重くって変化が見えにくいとしても、彼らの心の中は大きく変わっていくはず。
それを見逃さないで見つけられたときの感動はなにものにも代えがたいと思います。
それを、自分の思い込みにせずに子どもや教員と共有するには、やはりICTの支援は有効ですよね。
次にこのエントリー
上記の記事から半年ぐらい経った2014年10月25日の記事
ここにはこんなことを書いています。
世の中の状況が変わってくればそれに応じて人は変わってきたのだと思います。
そう考えると,学校の中で支援機器などを子どもたちの必要に応じて使えるような人というのは,常に学ぼうという姿勢があるかどうかなのかもしれません。
そのためには,自分の考えだけに固執せず,人の話が聞けることが大切だと思いますし,常に学ぼうとする姿勢を持つことなのかもしれません。
学校の先生は教えることが専門のはずですが,本当は自ら学ぶことも専門になって欲しい。
その姿勢を見せることが子どもたちの学びを広げると思います。
そのためにも,先生方が自分で学ぶ時間を作ってもらいたい。新しいことが入ったときに「面倒なこと」と感じるのか「面白そうだ」と感じるのでは180度違う。
そして、チャールズ・ダーウィンのこの言葉を紹介しています。
『最も強い者が生き残るのではなく、
最も賢い者が生き延びるでもない。
唯一生き残るのは、変化できる者である』
チャールズ・ダーウィン
夏休みというのは、私が教員に成り立ての頃に比べるととんでもないぐらい忙しくなっています。
でも、ちょっとだけでも子どもたちを離れる機会があるこのときに、それまでにはできなかった新しい学びを経験してもらいたいですね。
できれば、学校とはかけ離れたものも。
関係が無いように見えて、つながっているものは沢山あるし、引き出しが多い先生ほど魅力的だと思います。
研修会も多くなって、義務感で参加するとその時間が無駄になる。
受け身で参加するのでは無く、自分から学ぶようにしてもらえるといいなって思います。
最後にこのエントリー
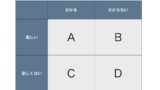
これは、3年前の2016年9月2日の記事を今年の3月に転載し直してました。
面白くなくても面白くしちゃえばいいのかなって思います。
板倉さんも「ころんでもしめた」っていっていました。
そんな風に学びを楽しんで欲しいですね。







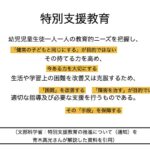
コメント