小さな子どもが自転車を練習する場合には最初は補助輪を付けていますよね。うまく操作することができると、片方だけ補助輪を外したりしながら、乗れるようにしていったりします。
こういった事って、教育の文脈だとよく行われています。
例えば、階段。
とても段差が大きいと、小さい子どもはたいへんなので、段差を解消するための補助の段を付けたりする。
からだが大きくなってきたらそれも必要なくなるでしょう。
以前、井上賞子さんが学習での支援ツールについて
自転車の補助輪としての使い方と眼鏡の使い方がある
というようなニュアンスでお話をされていました。
たしか、文字の学習だったかと思います。
井上さんの場合は、子どもたちの特性をよく理解し、適切にその使い分けをしていますので、心配ないのですが、子どもたちのことを理解していない人は、やたら支援を外したがる傾向があります。
それは
自立できないから
という考えから。
場合によっては、最初から使ってはいけないという人もいます。
しかし、そうなのでしょうか?
おがっちこと小川修史さんはTwitterでこんなことを書いています。
「支援や配慮をすると、手が離れた時に自立出来なくなるのでは?」
これ、むしろ逆なんです。「環境を工夫すれば能力を発揮できる」という事実を本人が認識すれば、本人に意欲が生まれます。意欲があれば自ら工夫や配慮要求ができる・・つまり、自立します。
支援や配慮は自立に不可欠なプロセス。
大切な視点ですね。
以前おがっちはブログでこんなことを書いていました。
おが「そのお子さん、自尊心を借金してますね。自尊心の貯金があれば、多少はガマン(支出)出来ます。でも、借金していると、すぐに爆発してしまいます。」
教師「自尊心の借金ですか。。」
おが「借金の状態やと、お金で頭が一杯。寄付なんてとんでもないですよね。自尊心も同じで、構ってもらうことで頭が一杯。思いやり(寄付)の気持ちを持ちなさいとか、ガマン(支出)しなさいとか、そんな状態じゃないんです。」
教師「とりあえずお金(自尊心)が欲しいということですね。」
おが「そうです。まずは借金を減らして貯金をする。その後に、クラスに入って行くことを考えてみてはいかがでしょう?」
教師「貯金をするために、5分の時間ということですね。」
おが「はい。難しいとは思いますが、どこかで貯金の時間を確保して下さい。」
引用元のブログが消えてしまったのですが、いまおがっちがこれをツイートしてもバズりそうですね。
大切なのはこころの貯金だったり、意欲の貯金でしょうね。
そういった自信を取り戻すために、支援機器があるのだと思います。
最後になりますが、奥平さんがnoteでこんなことも書かれています。
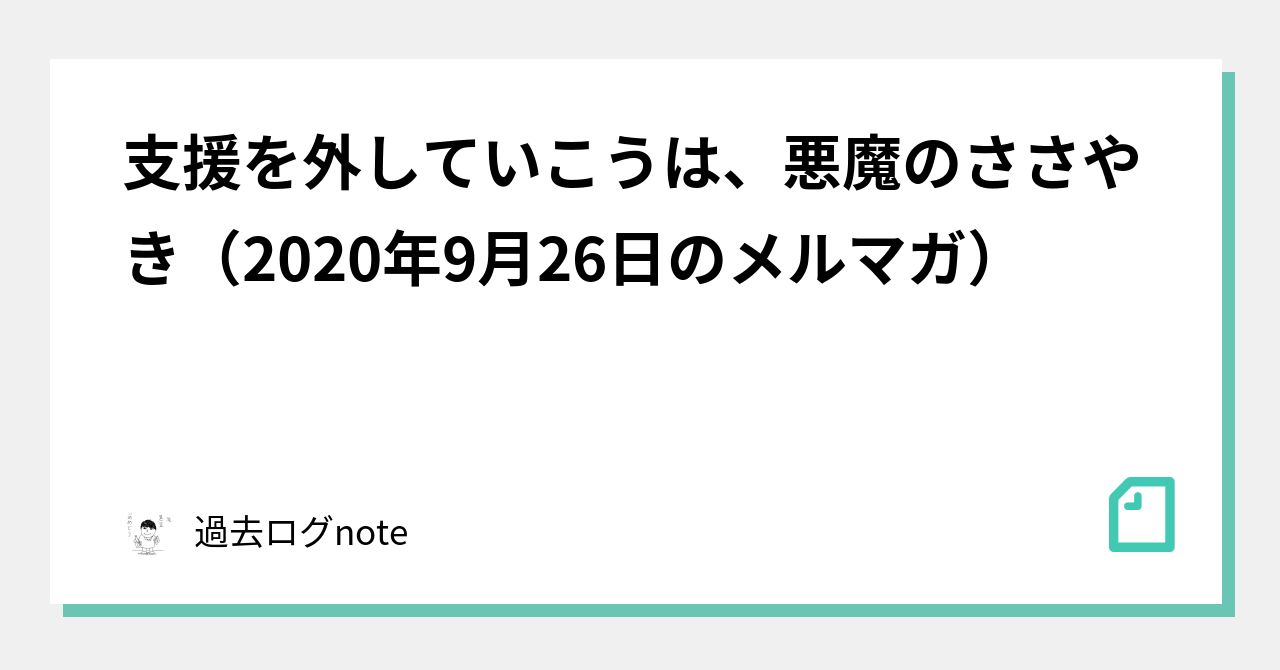
これをFacebookで紹介したところ、
プロンプトを外すのと混同していない?
や
支援と指導の手立てでを混同してない?
というコメントをいただきました。
まさにそうですね。最初の紹介の井上さんの場合はそこが適切に行われていると思います。
これはまさに道具の話しではなく、人の話だと思いました。









コメント