最近こちらの記事がネット話題になっています。

『ごんぎつね』の読めない小学生たち、恐喝を認識できない女子生徒……石井光太が語る〈いま学校で起こっている〉国語力崩壊の惨状 | 文春オンライン
少年犯罪から虐待家庭、不登校、引きこもりまで、現代の子供たちが直面する様々な問題を取材してきた石井光太氏が、教育問題の最深部に迫った『ルポ 誰が国語力を殺すのか』を上梓した。いま、子供たちの〈言葉と…
それは、かの有名なごんぎつねの1シーンで兵十が鍋を煮ているシーンを子どもが「死んだお母さんを鍋に入れて消毒している」「死体を煮て溶かしている」といっているという事です。
これだけ見るとドキッとしますが、こちらでは、題材としてのお話の設定が古すぎるとか,そんな発問がいいのかという述べられてました。
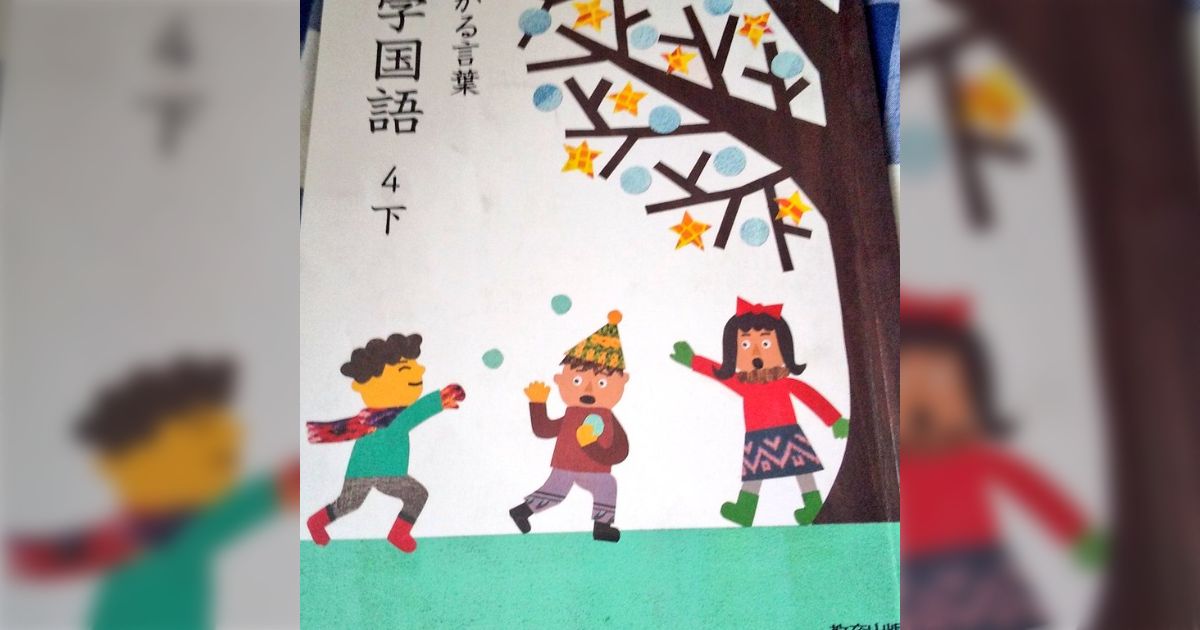
『ごんぎつね』鍋で母の死体を煮ていると答えた小学生の話から、国語力の欠如を懸念する意見と子どもの想像力を全肯定する意見
著書の内容を読んでないとわからない面もありますが、記事に対する感想や意見をまとめました
なるほど、そう言う指摘もある面ではあってますね。
お葬式に参列するという経験はいまの子どもはとても少ないでしょうから。
でも、ごんぎつねと言えば国語教育ではとても有名な題材です。
そんな単純なもんじゃないのではとも思います。
私は、単に国語教育というものだけでなく、社会全体や子どもが置かれている状況の分析も考えないと危ういなと思います。
よく読んでみると、こちらの本の紹介記事なんですね。
さて、実はそれよりも気になったのは、この記事の四ページ目のこちらに書かれている内容。

(4ページ目)『ごんぎつね』の読めない小学生たち、恐喝を認識できない女子生徒……石井光太が語る〈いま学校で起こっている〉国語力崩壊の惨状 | 文春オンライン
(4ページ目)言葉による感情の細分化――そうした子供たちの国語力を回復するにはどんな手立てがあるのでしょうか。石井 たとえばコミュニケーション不全の不登校の子たちに対して、あるフリースクールでは自分の感覚や気持ちと…
福岡にある少年院や刑務所を出た子供たちの再犯防止教育に力を入れるヒューマンハーバーそんとく塾の、「言葉のバブル」という授業です。
同じニュアンスの言葉をいくつか示して、それらの言葉の強さを大きなマルや小さなマルに入れていくという事。
知的障害教育や発達障害教育などでは声の大きさを視覚的に表すことで理解させるなどされています。
この実践ではこうしたことで感情のグラデーションを理解してもらい、再犯防止に役立てるとのこと。
調べてみるとこちらですね。
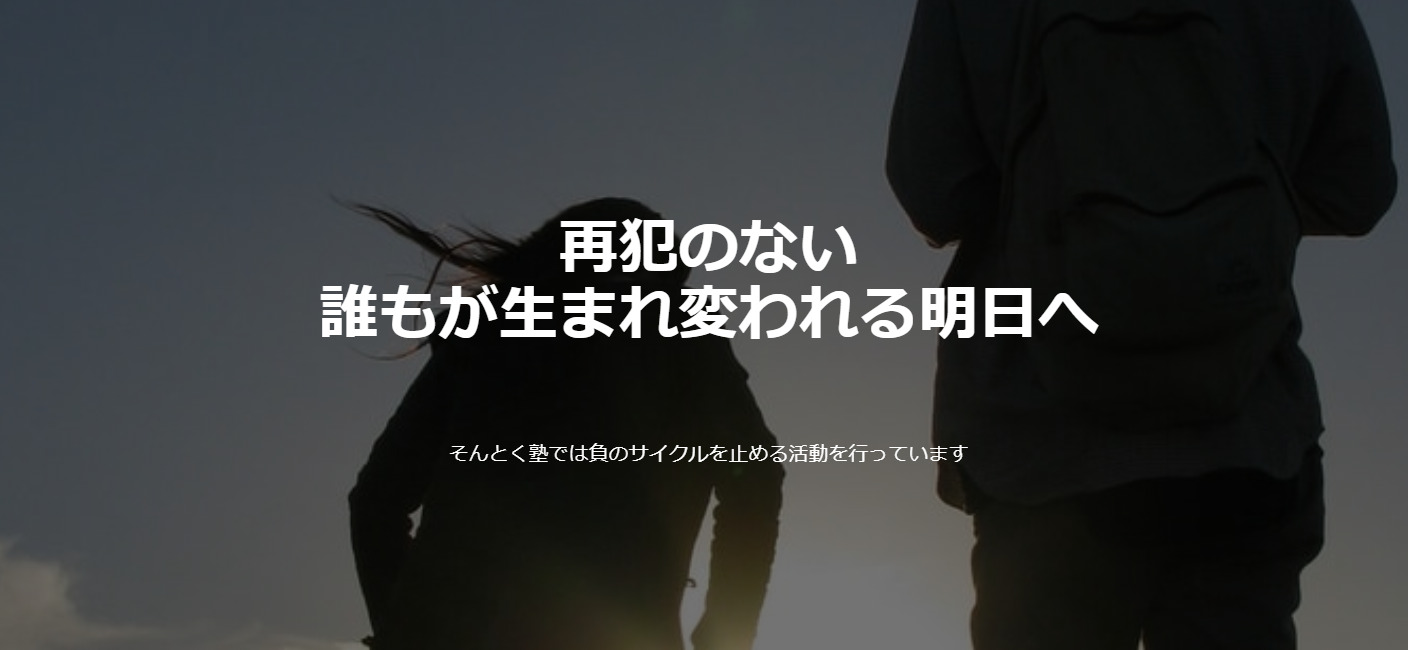
再スタートを支援する -そんとく塾
社会の歪はますます強くなっていきます。その中で漏れ落ちてしまう人も居ます。その原因を当人だけに負わせない為にそんとく塾では様々な支援活動を行っています。
そのまま使えるとは思えませんが、感情の強さを視覚的に表現していくというのはとても大切な気がします。
繰り返しですが、課題は国語力のことだけではない気がします。









コメント