本日は文部科学省とオンラインのハイブリッドでこの会議が開かれているそうです。

不登校に関する調査研究協力者会議(令和3年度第6回):文部科学省
これまでの会議資料はこちら

不登校に関する調査研究協力者会議(令和3年度) 開催状況:文部科学省
不登校については、以前紹介したように個人の課題とするよりも、社会的な問題も大きい。

日本財団の調査から考える「特別扱いはできない」といって排除される子どもがこれだけいてもいいのか?
先日のATACで中邑さん講演で引用した日本財団の調査です。文部科学省が不登校の基準としてあげているのは連続又は断続して年間30日以上欠席し、「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくと
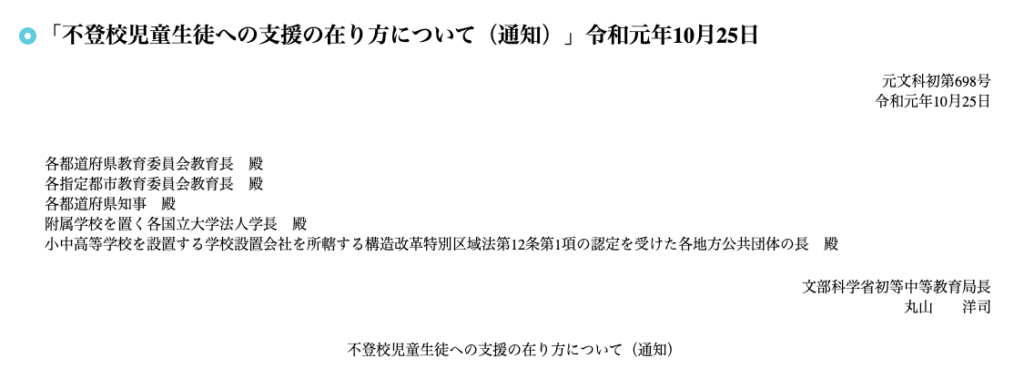
文部科学省・「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日
文部科学省が表記の通知を出しました。この中では登校できない状態にある子どものICTを活用した指導の扱いについても書かれていますが、本質的なことはそこではなく、彼らにとって学ぶことが楽しいと思える指導をすることだと私は思います。以前紹介したこ

【文部科学省】児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査
yahooニュースでこんな記事を見つけました。この記事の分析の元は文部科学省が経年で調査をしているこのデータです。多くのマスコミではコロナによって不登校の数字が増えていると書いています。しかしそれだけでしょうか?Yahoo!ニュースの記事を...
つまり本人の課題に帰属して考えるのではなく、私たち係わる側の問題として捉えていかないと解決しないと思います。
とても重要な会議ですね。
会議の方向性をよく見ていきたいと思います。










コメント